| 巨人の野球からみえる私たちの姿 | ||||||||||||||||||||||
| 1.はじめに | ||||||||||||||||||||||
| わたしは子供の時からの巨人ファンである。しかし昨今の巨人の野球を見ていると実に不快で、いろいろと考えさせられることが多い。どうしてあれだけ著名な選手を集めてあのざまであるのか。野球というゲームの成り立ちをどう考えているのであろうか。また、いつまであのようなチーム運営を続けるのか。その結果としてどれほどの若い選手を育ててきた、いや潰してきたのだろうか。そして、あれほどの選手を鳴り物入りで入団させて、あのような成績をとったときの責任はどこにあり、誰がその責任をとるのか。このようなことは巨人の野球、あるいは野球の世界にだけ限ったことなのか。このようなやり方の社会に与える影響はどうなのか。このことをきちんと批判せず、相変わらず巨人巨人と騒ぐマスコミの体質とは何か。やはり視聴率と新聞発行部数の世界なのだろうか。止めどもなく頭は回る。“バカ!、そんなことよりもっと大事なことが一杯ある”、と怒られてしまいそうでもある。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.昨年の巨人の優勝はなぜ可能だったのか? | ||||||||||||||||||||||
|
一言でいえば、広島が自分でこけた以外のなにものでもない。10ゲーム以上の大差をつけていた広島が多くのけが人を出して自己崩壊してしまったのである。それでも巨人が勝った理由がどこかにあることに間違いはあるまい。それを探してみることにしよう。
それは選手層の厚さであろう。攻撃陣、守備陣とくに投手陣はともに多くの人材を抱え、選手層の薄い他チームを出し抜いたのである。とくに救援投手陣を支えたのは移籍によって獲得した川口や河野であり、とくに後半戦に急遽投入されたマリオは救世主的存在となって崩壊した救援投手陣を守ったのである。それとて急遽の輸入であり、マリオがさらに育って今年も活躍するといった状態にならなかったことは、一時しのぎの体制であったことを如実に物語っている。つまり、ただ目先を変えて相手を撹乱しただけのことであった。 では、攻撃陣はどうであったのだろう。松井は超一流への道を歩んでおり、落合もそこそこに働いて問題はなかったが、ヤクルトから鳴り物入りで入団して2年目の広沢は働けず、その窮状を救ったのはなんと若手?の元木、大森、後藤、清水、出口らのはつらつとしたプレーであった。彼らは優れた素質を持ちながら、これまでそれほどのチャンスを与えられたわけではなかった。その彼らに球団運営の失敗の穴埋めとしてチャンスがめぐってきたのである。皮肉なことに彼らは見事に素質を開花させ、巨人の窮状を救ったのである。 これら外から補強された者とチャンスを待ちわびていた控えの選手達が昨年の巨人の優勝を支えただけのことであった。何とも淋しい限りである。 |
||||||||||||||||||||||
| 3.さて今年の体制はどうなったか? | ||||||||||||||||||||||
|
今年は上に述べたような若手を中心としてチーム編成を行うのかと思いきや、全く違ったものになってしまったのである。一昨年は「攻撃野球」を目指して広沢をとり、失敗すると「守りの野球」を目指して川口、河野をとってマリオの救援と相手チームの自壊を受けてやっと優勝したことをすぐに忘れてしまったのであろうか。なんと「守りの野球」とは関係のない清原をFAで取ったのである。これだけではない。マックを解雇し、守備に不安のあるルイスをとり、最近では昨年の柳の下の2匹目のどじょうをねらって、カスティヤーノと救援投手としてのデイビットを獲得した。これらの選手は昨年活躍した若手達を先発メンバーから追い落とすには十分すぎるほどの数であり、「守りの野球」とやらはどこかにすっ飛んでしまったのである。さらに、今季入団した新人投手入来と三沢を直ちに救援投手として使うことを早々と宣言した。巨人にはそんなに若手の有望な投手は育っていないのだろうか。韓国から鳴り物入りで入団した趙もいる。いまやメジャーリーグ、ニューヨーク・メッツの中継ぎ・抑えの重要な一員になりつつある柏田も、またどこかに移籍した吉田(修)、石毛、香田などなど数え切れないほどいたし、今も居るのである。
結論をいえば、巨人の球団運営のなかには着実に選手を育て、その選手を信頼して戦っていくという姿勢が全く見えないのである。これは長い間培われた巨人の体質である。常に大物選手を引き抜き、それによってそれなりの成績を挙げてきた歴史がある。そのことが、全国的レベルのファンの獲得と維持に貢献し、球界の中にアンチ巨人の反体制派の発生をある程度抑制してきたのであろう。選手の獲得競争を自由市場からドラフト制に変換されてもなお、強引な手法を用いて選手を獲得し、そのドラフトァの問題が明るみに出れば「逆指名」を可能にするとともにフリーエイジェント制を導入して多くの選手を集めてきた。しかし、いっこうに選手育成の方針が見えてはこないのである。 |
||||||||||||||||||||||
| 4.選手はどこで育つのか? | ||||||||||||||||||||||
|
昨年ロッテの広岡ゼネラルマネージャーは一昨年好成績を挙げたバレンタイン監督を解任した。わたしの感覚からこれを見ると次のようになる。つまり衝突の原因は、バレンタイン監督が「与えられた戦力でいかにうまく戦うか」を目標にしたのに対し、広岡マネージャーは「いかに育て戦うか」を目標としたからだと見られる。広岡は、日本のプロ野球の水準を“これから伸ばしていかなければならない選手の集団”と見るのに対し、バレンタインはそれは目標ではないと感じていたようである。
最近興味深い事件が発生した。ディミューロ事件である。これは周知の通り日本の審判とアメリカの審判の置かれている位置の違いを明確に示したもので、極めて興味深い。この事件から明らかになってきたことのひとつに審判の教育システムの違いがある。アメリカにはれっきとした審判学校が設立されており、彼らはメジャーリーグ傘下の1A、2A、3Aのマイナーリーグで腕を磨きながら訓練を受けているのである。常にメジャーリーグからの厳しい評価にされされながら、彼らの内ごくわずかの選ばれた者だけがメジャーへの昇格を許されて行く。そこには立派な教育システムが存在する。 これに引き替え日本の場合はどうか。それとは全く異なり何もないといって過言ではない。多くの審判は野球選手としての将来を失って、審判の世界に活路を見出そうとする者が多いのが実状であり、審判全体の半分近くを占めている。従って、選手の側から見れば審判は一段低く見られがちな運命にある。審判育成のしっかりとしたシステムもなく、従って審判はストライク、ボール、アウト、セーフをコールするだけの意味しか持たず、“ゲームをコントロールする”という本来の役目を果たすことを基本的には要請されていないとみられる。 プロ野球選手の育成の場合も基本的には同じ問題を抱えている。近年、日本では一軍でないチームのことを「ファーム」と呼ばれるようになりつつあるが、一般的にはいまだ「二軍」と呼ばれ、教育的意味を持ったものとは考えられてはいない。しかも、アメリカのように1Aから3Aまでのような膨大な教育組織を持っていないために底が浅く、選手層も薄いのが実状である。従って広岡マネージャーの言うように、きちっとした教育が必要であるとの認識が出てくるのであろう。それは正しい。 日本の二軍における教育とはどんなものなのであろうか。二軍のコーチ、監督のほとんどは選手生活を終えた後すぐか、あるいは2、3年ネット裏で“勉強”した後に就任するのがほとんどであろう。ここで問題になる点が2つある。ひとつは、教育を担当すべき人たちが“教育するものとしての教育”を受ける土壌がないこと、2つ目は日本のスポーツ界に隠然と存在する縦社会の弊害である。特に野球の世界に有名な“しごき”という猛練習は、若い選手から考えるゆとりを奪うものとして機能し、先輩・後輩の縦関係のつながりは上級生による下級生への陰湿ないじめとして相変わらず存在することは日常新聞の報ずるところである(最近のPL高校での事件は例外ではない)。これら2つは、日本におけるスポーツ教育を著しく歪めてきた元凶である。スポーツ界は新しい理論の導入の最も遅れた分野のひとつであり、個性の発揮が最も阻害されてきたところである。近年“しごき”という言葉は一見死語になりつつあるが、先輩・後輩の縦関係の悪弊が是正されない限り、教育という観点からみたときにはまともな土壌の形成は絶望的である。 |
||||||||||||||||||||||
| 5.スポーツは首から下でやるもの? | ||||||||||||||||||||||
|
高校野球を初めとして多くの学校のクラブの監督は、そのほとんどの場合OBが監督やコーチを勤めている。また最近問題になっている明治大学のラグビー部も同様であり、チーム内の教育体制それ自体が明確な縦社会の構造をとっている。OBというのは一体何であろうか?学校側はOBに経済的な支援を求め、OBは指導者の予備軍として機能する。一体いつまで害毒を流し続ければわかるのだろうか。かって、日本サッカー協会の重鎮のひとり岡野俊一郎氏は、“日本のスポーツ関係者はスポーツは首から下でやるもんだと思っている”と喝破した。
確かに新しい時代に目を向けなければならなくなっている小学校、中学校や高校の現場では、少しずつではあるが事態は変わりつつある。また、新しい観点を持ってスポーツ界に殴り込みをかけたJ−リーグの存在はこの傾向に拍車をかけつつある。しかし一方では、依然として監督・コーチによる自分の体験を基礎とした教育のみという事態を防げない事情がもうひとつある。 私と私の家族がアメリカで生活した1年ほどの経験を少し述べてみよう。私の子汳B(男二人、女一人)はサッカーのクラブチームに属していたので、私は試合や練習に絶えずつき合うことになった。そこでみた光景は日本とは全く違うものであり、いわゆるカルチャー・ショックを受けることとなった。例えば、監督やコーチは試合の合間であるハーフタイムに、それまでの選手の動きや作戦について子供達に分かり易く説明した後、選手達から意見をきくが普通である。その時選手諸君は、それがレギュラーであれ補欠であれ、自分たちが思っていることを存分に表現する。また同時に、応援に駆けつけていた親達の振る舞いが不満であれば堂々と批判することになる。この繰り返しが遠い国アメリカのスポーツ界で行われている教育である。そこには、教える側も教えられる側も自分の意見をきちんと表現することが基本となっており、それを土台として、全体のシステムが構築されているのである。そこには、監督・コーチや先輩の言うことは絶対であり、選手や後輩はただそれを聞いて実行するのみというような不毛な関係は存在しない。この点が日本との最も大きな相違である。 日本のスポーツ界が、その国技とも思われるほど選手層の厚かったはずの野球の分野でも相変わらず大きく後れをとっている状況は、教育そのものが不毛である土壌が潜んでいるように思われる。その中で、新しいフィジカル・トレイニングを目指した立花前ロッテ(その前には近鉄に在籍)コーチがアメリカに行かざるを得なくなった状況は象徴的であり、これが野球の世界で起こっていることに注意すべきであろう。最近アメリカの野球リーグで、野茂をはじめ長谷川、柏田、伊良部などが活躍しはじめて注目を集めている。一見日本の野球の世界が順調に成長しているような錯覚にとらわれるが、しかし彼らがネガティブな意味でアメリカに出向いている実状を考えると暗澹たる気持ちである。実はその野球人口からいってとっくの昔にもっと大勢の大リーガーが誕生してもよかったと考えるべきなのであろう。 最近、近頃の若い者はきびしい練習が嫌いで、というような言葉を耳にすることが多い。それはきっと納得の出来ない練習は嫌い、という意志表示として聞くのが正確であろう。最新の理論で武装し、J−リーグを土台とした新しい教育システムを取り入れたサッカーは、ワールドカップに出場したことがないとはいえ、今や世界ランキング17位という驚異的躍進をはたした。これは、かってアジア勢がなし得なかったはるか高い位置であり、また20歳以下のワールドカップといわれるU−20世界選手権大会で日本チームは、2大会連続のベスト8進出を果たしている。これらのことについてはその内容としてもっと評価されるべきことである。観客動員数が減っただの、フランスワールドカップに行けなければ何にもならないなどとマスコミは勝手なこと言っているが、そのことこそマスコミの底の浅さを示しているに過ぎない。何十年もプロをやっている野球の世界と比較すること自体がナンセンスである。このような状況の中で、個人的競技の色彩が強く、新しい理論と練習システムを取り込み易い個人競技に近い分野であるスキー、スケート、水泳・陸上競技などが世界にはばたきつつある現状は、あらためて野球の世界の遅れを痛感させられる。しかし全体としてみれば、依然として日本のスポーツ界は世界から大きく立ち後れていることに変わりはない。 今年前期のJ−リーグを制した鹿島アントラーズの監督J.カルロスは、プロサッカー選手としての経験はないが指導者として輝かしい業績を持っている。彼は大学でサッカー理論や栄養学を学んだ屈指の理論家であることを考えると、経済大国ではないブラジルの底の深さを感じざるを得ない。 |
||||||||||||||||||||||
| 6.学校はどうなっている? | ||||||||||||||||||||||
|
上に述べてきたような事情は、同じ社会に存在している以上学校にも当てはまるのではないかと考えるのは当然である。大学に籍を置くものとしてはこのことを痛感している。大学で教育を担当すべき者として在籍している私たちは、実はそれぞれの学問分野においてそれなりの研究業績を上げることによってその籍を得たのである。通常、小学校、中学校や高等学校の先生になろうとすれば教育をするに必要だと考えられる分野の教育をある程度受けることが義務づけられており、それを欠いては絶対に先生にはなれないことになっている。このことは、社会の基盤を構成するであろう未だ成熟していない若年層の教育を担当することの重要性から当然要求されることとして理解される。しかし、それにもかかわらず小学校から高等学校に至るまで学校教育の抱える問題は多彩で、複雑で深刻であり、日本の教育システムの根幹を揺るがし続けている。
しかし、奇妙なことに大学の先生にはこのことが全く要求されていない。それは多分、大学に入学してくるような世代の若者はすでにある程度の精神的な安定性と自覚を持ち、勉学意欲に満ちた者達であるとの前提に立チているからだと思われる。従って、大学の先生達が各分野で先端的な研究業績を挙げることにその大半の時間を割き、それを教育の課程に導入したとしてもそれを受け取る能力を十分に持ち、それをさらに継承・発展させてくれるものとの暗黙の前提が存在する。また、その真摯な研究態度を学ばせることの中にこそ新しい世代を生み出す原動力が存在すると信じるのである。 素直に見れば、日本の大学の先生とプロ野球の監督やコーチの姿は二重写しに出来るのである。つまり、自分たちの後ろ姿を見せることが教育なのである。一人一人の大学人としてはそれはそれでよいのであろう。大学の人間はこの点さえ全うしていないとの批判は確かに存在するが、もっと大きい「大学という教育機関」としての問題は、上に述べたような暗黙の前提が成立しているかどうかにかかっている。この問題は一体、誰が、どのような組織が調査・研究して解決するのであろうか。 |
||||||||||||||||||||||
| 7.どこまでも個人的な縦の世界 | ||||||||||||||||||||||
|
たとえそれがスポーツの世界であれ学問の世界であれ、教育というものは、教育を担当する人間が自らの後ろ姿を若い人たちに見せることにあるとすれば、組織的であるというより個人的なものであるということになる。それはそれでいいのかもしれない。しかし、このことと縦社会の構造が関連すると、それだけに留まらず、他人または他からの不介入を原則とするという構造に変わってしまいがちである。そして教育関係には必須と思われる「柔軟性」が抜け落ちていく。すなわち、自分と異質なものが教育対象の中に出現したときには制御不可能になることを恐れ、教育対象が教育者である自分の枠外に出ることを許さない。このことがさらに上下関係の強化につながることとなり、教育される側から教育する側を上回る内容のものが出現することは滅多にないこととなる。
これに加えて日本の社会には親子・上下関係を重視する考えが古くからある。この二つが相まって今の日本の社会体制を作り上げており、抜き差しならない状態になっている。つまり無意識となっている上下関係を自覚させ、それを越えて新しいものを作り上げていくはずの教育現場が、その役割を果たしていないのではないかと思われるのである。最近の新興宗教の問題、薬害エイズ事件、野村証券・第一勧業銀行等の問題、また学校への不登校の問題、最近の関西での少年による凄惨な事件、どれをとっても上には逆らえない日本社会の構造的な問題が浮かび上がってくる。 |
||||||||||||||||||||||
| 8.再びスポーツと学問の世界 | ||||||||||||||||||||||
|
アメリカという国は個人主義の国といわれる。そしてその故に様々な問題を内包している国ではある。しかし、その個人主義を貫くためにかアメリカにはそれを保証する組織性が存在する。一見奇妙に見えるが、個人個人はそのシステムの中できっちりと評価され続けているのである。そのことが個人個人の無政府的な突出を抑え、権利とともに義務を課す構造になっているようである。つまり、メジャーリーグを頂点として1Aの裾野までのピラミッド構造がひとつの組織をなし、それを自由に自己表現する個人が支え、また個人で守れない領域の問題に対しては組合を持って対抗する構造が縦横に入り交じって組織全体、社会全体を支えているのである。審判の組織もこれと同じ構造である。メジャーリーグの選手組合、審判組合にみる通り、これらの組合は現在の日本の組合に比べてはるかに強大な権力を持ち、ラディカルである。大学を頂点とする教育システムも基本的にはこれと同じ構造と考えても良さそうである。大学の先生も、その研究業績はもとより、その教育における評価を大学またはその連合体のようなものから受け、学生側からも審判を受けるようになっているのである。アメリカはとんでもない自己中心的な行動をとる国ではあるが、しかし、しばしばそれを修正する「柔軟性」を持っていることも事実である。
はたして日本はどうか。プロ野球はほとんど組織性を持たず、従って教育組織としても機能できない。その結果、どのような教育を行うか、それをどのように生かしていくかはそのチームの指導者の個人的な問題であって、やってもよし、やらなくてもよしということになってしまう。どこがやっていてどこがやっていないかは誰がみても明らかであり、その中で特筆すべきは、日本に見切りをつけ、ドミニカに野球アカデミーを設立した広島カープである。ほとんど自前の選手ではつらつと戦うこのチームを我々はもっと応援したいと思う。また、故障した選手や他球団から見放された選手を、また若手をよく教育して戦うチームなど、リーグ全体の組織性ではなく個人的なレベルでよく考えているチームもあることは指摘しておかなくてはならない。 大学は学問の自由の旗印のもと、各研究単位、学部・学科・大学院の縦割りになっており、具体的に何を伝授するかというカリキュラムの検討以外にはほとんど組織だった教育改革は行われてこなかった。従って学生の教育をどうするかの前に、大学の先生の教育を組織的にどのように行うかの検討が急務であろう。さらに、大学がまっとうな教育を行うつもりがあれば、入学してくる学生がどのような人格・特質を持ち合わせているかの検討が必須と思われる。大学は現在改革オンパレードである。改革しなければならないことは、教育に研究に山ほどある。残念なことに、こと教育に至っては如何に先生方が個人的に努力されようとも、それを大学として解決して行くためのシステムが保証されていないのが現状である。また、ここではほとんど問題にしないが、自分たちの命運を握っている研究の場合でも、研究内容の深化や、研究環境の改善の努力が、粘り強く批判的な討論の中で行われているかについては多くの疑問がある。 第6章でも述べたごとく大学での教育は、精神的安定性があり、勉学意欲も自覚もある学生の入学を暗黙の前提としている。この問題は人間そのものの問題であり、文化的・経済的・社会的問題を内包しているはずである。そうだとすれば、そのような分野の学者が多くの力を発揮するのが当然であるが、敗戦後重工業化社会を目指してしゃにむに理科系を重視して拡大してきた大学にはその力がないとみるのが妥当であろう。所詮は、成り上がりの経済大国・日本の姿である。 |
||||||||||||||||||||||
| 9.最も困ったこと | ||||||||||||||||||||||
|
それは、特に若い人たちが際だってものを言わなくなったことである。大学での授業で一番消耗することは、学生諸君がうつろな目をして座っていることである。質問を促しても全くという程なく、そうかといって分かっているわけでもない。自分が感じていることを口を開いて表現することは、あらゆることの基本ではあるが、それをするよりは黙っているほうがより楽な生活を送れる社会になっているのであろう。したがって、若者の寡黙さが“最も困ったこと”ではなく、当然のことだが、この世界を作り上げてきた私たちが、率直に自己表現し、それを契機として物事を考える習慣を持たずに育ってきてしまったことの方に責任がある。
かって私も野球少年であった。その時のことを考えても、また今いろんなスポーツを観戦に行っても、たとえば監督・コーチの指示に対して選手側が積極的にものを言うというような光景に出会ったことはほとんどない。ほとんど一方通行的な意志の流れしか感じられなかった。自己表現のなさはいずれも日本の縦社会の現れであるが、事態を改善する方向に行かせない大きな要因のひとつでもある。これを乗り越えるチャンスは今まで度々あったが、残念ながらいずれの場合にもそれを生かすことはできなかったのである。 |
||||||||||||||||||||||
| 10.おわりに | ||||||||||||||||||||||
| 巨人の野球から書き始めて大学のことまで書いてくると、日本の社会にはそれぞれの部門をきちんと自己管理し運営する組織性がほとんどないことが分かる。あるのは自分自身をいかにすれば守れるかを思案することばかりである。従って他人のことに口を出すなどもってのほかで、他人のことに口を出せば後ろから何が飛んでくるかも分からないのである。このような状況を強化してきたのは今の大人達である。その意味で私たちの責任は大きいが、出来ることから、つまりタマネギの皮を一枚一枚剥いでいくようなことをしなければならないのであろう。それぞれにつらい仕事である。しかし、それだけの批判力を自分自身が現在持ち得ているか疑問である。自分のやっておきたい研究に精を出すのと、これまで書いたような問題に口を出すのとどちらが今まで活かせてもらった社会に対する貢献が大きいのかを考えると複雑な気持ちになってしまう。 | ||||||||||||||||||||||
| 11.再び、おわりに | ||||||||||||||||||||||
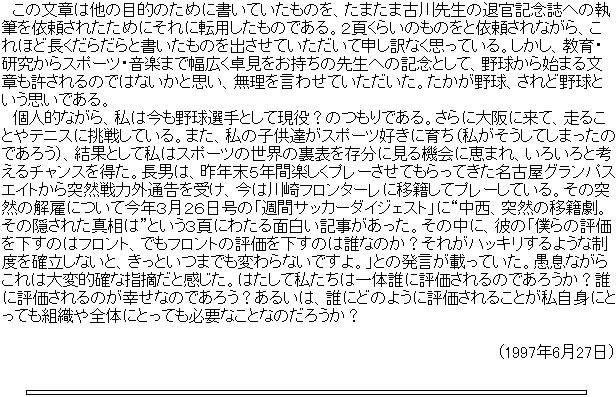
|
||||||||||||||||||||||