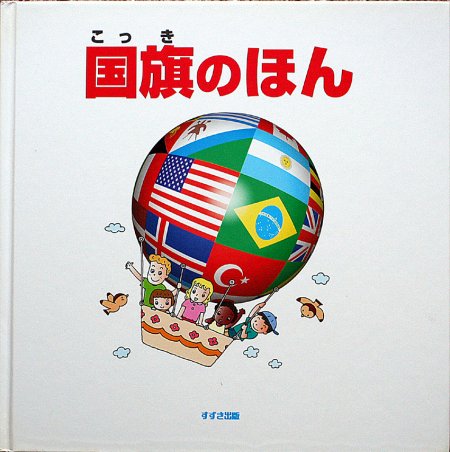一時代を築いた“なでしこ”と 加齢に脅かされる“年寄りランナー”のやるべきこと
- 2016/03/11 22:30
最初の写真でお分かりのように、あの“なでしこ”が大阪でのアジア最終予選第4戦の対ヴェトナム戦を前についに4大会連続のオリンピック出場権を失ってしまった。ドイツワールドカップ優勝、ロンドンオリンピック準優勝、そして昨年のカナダワールドカップ準優勝と快挙を続けてきた“なでしこジャパン”の栄光を知るファンにとっては大きな衝撃と落胆であることは至極当然である。その原因についてここぞとばかりに書き始めたマスメディアの姿にはいささか辟易としている。負ければいつものことであるがゴシップめいたことを沢山書くからである。 敗北の原因はメディアが書くようにきっとさまざまであろうことは想像に難くない。選手と監督の間の溝、選手間の溝、お互いにうまくいかなくなれば愚痴も出始めるのはどこの世界でも同じであろう。そんなことを言ってみても始まらない。むしろそんな当たり前の愚痴は出た方がよいのである。それをポジティブに聞けば前を向ける。
敗北の原因はメディアが書くようにきっとさまざまであろうことは想像に難くない。選手と監督の間の溝、選手間の溝、お互いにうまくいかなくなれば愚痴も出始めるのはどこの世界でも同じであろう。そんなことを言ってみても始まらない。むしろそんな当たり前の愚痴は出た方がよいのである。それをポジティブに聞けば前を向ける。
そんなことより構造的な問題の方がはるかに大事だと私は確信する。その最も大きな問題は世代交代が進まなかったことであろう。私から見れば当時ほとんど若手が育まれる地盤のなかった日本の女子チームが、ワールドカップで優勝や準優勝したり、はてはオリンピックで準優勝したりなんてことは、ほとんど“奇跡”だと考えるべきことであろう。そんな奇跡が三度も続いたのであり、奇跡を通り越して破天荒なことと考えるしかないのである。だから、とんでもないレジェンドと呼んでもよいような指導者や選手たちがいたのである。だから私には“なでしこジャパン”に感謝以外の言葉はない。
私の拙い知識から言えば、たとえばアメリカの女子選手は、正確ではないかもしれないが、およそ200万人いるといわれ、日本とは桁が2つは違うのである。しかも、彼女らのプレーを見た経験から言えば、恐ろしいほどの迫力で、男子顔負けである。高校生のゲームで腕を骨折した試合を見たことがあるが、 なぜあれほどのプレーをする選手がごろごろいるのかの理由は全く分からないが、それは彼らの生き様であろう。ただ、活動的なアメリカ女性には男子に開かれているようなベースボール、アメフトそしてアイスホッケーのような道が開かれてはいないからかもしれない。いずれにせよ、その中から選抜されてくるチームがなでしこが戦ったアメリカチームであり、彼らに勝つ、あるいは対等に戦ってきたのである。したがって、構造的な問題とは、いかに底辺を拡大し、いかに小さな底辺から優れた選手を育成する方策のことでなければならない。
なぜあれほどのプレーをする選手がごろごろいるのかの理由は全く分からないが、それは彼らの生き様であろう。ただ、活動的なアメリカ女性には男子に開かれているようなベースボール、アメフトそしてアイスホッケーのような道が開かれてはいないからかもしれない。いずれにせよ、その中から選抜されてくるチームがなでしこが戦ったアメリカチームであり、彼らに勝つ、あるいは対等に戦ってきたのである。したがって、構造的な問題とは、いかに底辺を拡大し、いかに小さな底辺から優れた選手を育成する方策のことでなければならない。
今回の敗北で、サッカー協会は世代交代の大切さが身にしみたであろう。きっと世代交代の実現に向かって進むことを期待したい。今回の最終予選の裏ではスペインのU-23ラ・マンガ国際大会が開かれていた。なでしこの最終メンバーに残れなかった選手たちが躍動してスウェーデン、ノルウェーそしてドイツなどの強豪を打倒したという。また、なでしこも最終予選最後の宿敵北朝鮮戦では1-0で勝利し、再び輝きを取り戻すきっかけとなる活躍を見せた(二枚目の写真)。私にはこれ以上のことを言う内容がないので、ただただ今後の積極的な世代交代を期待したい。しかし、それは単純な年齢の問題ではないことは明らかである。 このように偉大な業績を残したなでしこと同列に置くなどおこがましいと言われそうであるが、私の苦しいところも書いておきたい。個人の問題に世代交代などありうるはずもないが、しかし歳を重ねることによる体力・競技力低下では共通している。勿論私には初めての経験で、それらに打ち勝つためには当たり前のようにトレーニングによる体力強化と、加齢とともに顕在化する故障の回避などに向けての走法改善や身体の使い方の変更などを考えないといけないのであろう。
このように偉大な業績を残したなでしこと同列に置くなどおこがましいと言われそうであるが、私の苦しいところも書いておきたい。個人の問題に世代交代などありうるはずもないが、しかし歳を重ねることによる体力・競技力低下では共通している。勿論私には初めての経験で、それらに打ち勝つためには当たり前のようにトレーニングによる体力強化と、加齢とともに顕在化する故障の回避などに向けての走法改善や身体の使い方の変更などを考えないといけないのであろう。
実は私には10年以上前から右腰の背部に表れるちょっとした違和感が気になっていた。それは少しずつはっきりとしたものに変わってゆき、昨年引越しをして生活環境、トレーニング環境が変わったことによるのか違和感がさらに強くなり、マッサージ師による治療を受けてはいるがなかなか治癒に向かう感じではなかった。この違和感、あるいは痛みが右腰の部分に偏っていることから、内臓などの関連痛でない限り身体の使い方に起因すると3か月ほど前から考えるようになり、特に主として身体を使うランニング動作の左右のアンバランスを検討することにした。
よくよく考えてみると以前から気にしていたことがいくつかあった。それはジムでの、鏡が前にあるトレッドミル上でのランニングの場合、しばしばいつの間にか右に偏って走る傾向があることと、T-シャツを着て走っているとシャツの首の部分がいつも右に偏ってそこに隙間ができてしまうことであった。また鏡をよく見ていると、右足の着地では足先が若干右に外旋することも分かっていた。さらに以前から息子から全体としてストライドが広すぎることと右のストライドが左のそれよりシューズ1/3足分ほど長いことも指摘されていた。このピッチ走法への変更は、加齢による筋力低下が故障発生につながらないようにするために重要だとは昨年「佐藤治療院」からも指摘されていた。
これだけのことを頭に入れてやるべきこととしては、全体をピッチ走法に変更することを確かなものとし、また右ストライドを短くして左右のバランスを取ることであった。その結果は驚きであった。右ピッチを短めにするように走ると、足先の外旋もなくなり、右に偏って走ることもT-シャツが右に寄れて首に隙間ができることも全くなくなってしまったのである。
こうして迎えた3月6日の立川シティハーフマラソンでは、高い気温にもかかわらずグロスタイム2時間09分34秒で余力を残して気持ち良く走ることができ、ふくらはぎなどの故障発生もなかった。今回の結果は、昨年秋の神戸マラソンの5時間30分というとんでもない内容(http://www.unique-runner.com/blog/diary.cgi?no=243 )に比べると全く別物で、近年感じていた寂しい凋落傾向に歯止めをかけることができたようで、久しぶりにまともに走ったという気持ちである。
だからといって右腰の違和感が消えたわけではない。走法の変更が直ちに違和感という感覚の解消に結びつくと考えるのは早計であろう。腰の痛みや違和感の原因は多岐にわたり、なぜか脳が主導権を持って“痛みがある”と感じているのだという新しい考え方は最近強い。私の場合、今回の様々な変更で違和感などが安定し、少しずつ改善されているように感じている。本当のところは、感じているのか感じようとしているのかはわからない。とにかく身体の使い方をバランスよくすることを持続してじっくりと腰を据えていきたいと思っている。
この様々な改善の努力は再び何とか新しい自分を作り出す方向を指し示しているように思える。世代交代が進まず、平均年齢が27歳と今回の予選大会で最も高かったなでしこのやるべきことも、明らかであろう。もともとフィジカルの強いオーストラリアや中国が技術レベルを上げ、さらにチームとしての戦略・戦術を高めてきた現在、なでしこが世代交代を果たしながら再び俊敏性とパスワークにさらに磨きをかけなければ、強豪のそろうアジアを抜け出すことは難しいであろう。
3枚目の写真は、応援してくれる人たちとハイタッチしながらゴール間近を走る私である。今回は4月17日の長野マラソンに向けてよい予行演習ができたと思っています。
最後に、ここの記述をお読みになった皆さんは、細かすぎるとお思いだろうと思います。しかし私にとっては一大事で、この腰の違和感の問題は放置すればどんどん悪化し、さらに高齢化したときの生き方に決定的な悪影響を持つと危惧しています。それは走るとか走らないとかの単純な問題ではないと思っていますので、放置することはできないのです。なお、この問題を考える過程で故障の予防的なマッサージを勧めてくれた「ちあき接骨院」に感謝したい。