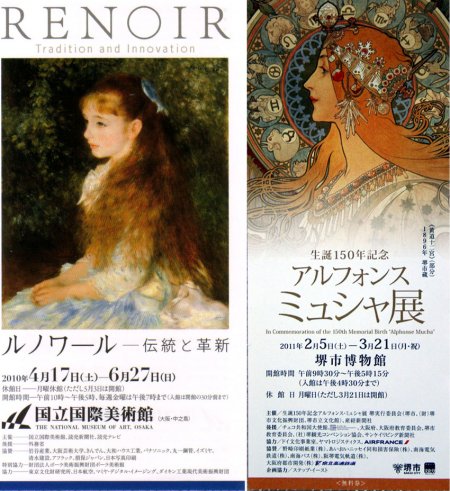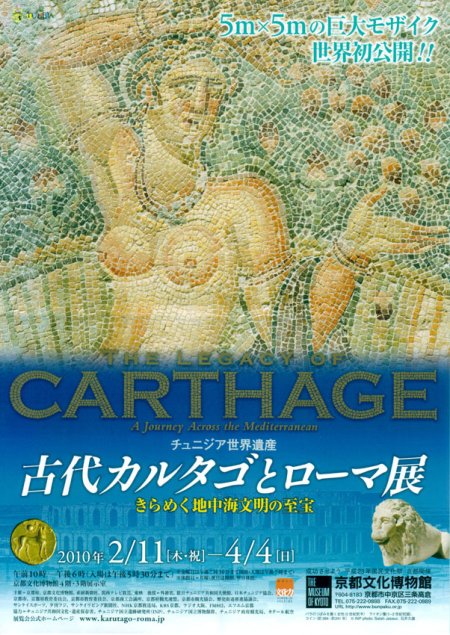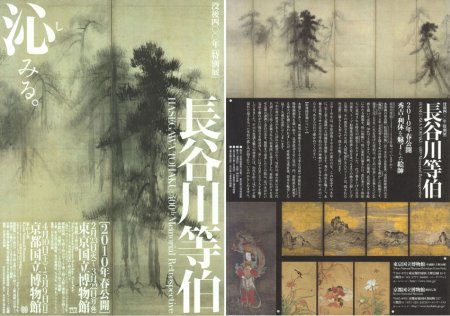[完全復元] というサブタイトルのついた記事が登場する!
- 2011/09/22 09:30
ブログのファイルが失われたということはすでに書いた。そのため、残った写真を参考にしながら当時書いたであろう文章を付けて復元したものを[簡易復元]と言うサブタイトルをつけて書いてきた。しかし、幸いなことに私が友人に託したブログ30編のプリントアウトが保存されていたことが分かり、それを譲り受けることができた。
しかし、残念ことにそのブログは2009年12月末から2010年8月までの中からの30編で、それ以外、特に今年3月11日に起こった東日本大震災関連のものは全く入ってはいない。それらについては、できるだけ記憶をたどってそのうちの幾つかについてでも[簡易復元]させたいと考えている。
それはともかく、今回入手できたプリントアウトを丹念に[完全復元]に持ってゆきたいと思っている。再度皆さんの目に触れることができれば幸いである。