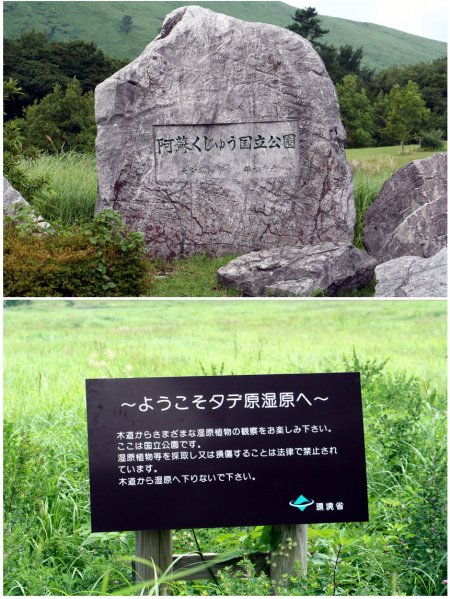[簡易復元] 大分から熊本までの九州横断ドライブ310キロの旅ー(4)岡城跡と瀧廉太郎
- 2011/09/17 16:32
 南阿蘇にあるホテルに向かう途中に竹田市がある。そこには岡城の跡が残されており、それにゆかりの深い作曲家滝廉太郎の記念館があった。岡城跡についてWikipediaは次のように言う。
南阿蘇にあるホテルに向かう途中に竹田市がある。そこには岡城の跡が残されており、それにゆかりの深い作曲家滝廉太郎の記念館があった。岡城跡についてWikipediaは次のように言う。
「岡城(おかじょう)は,現在の大分県竹田市大字竹田にあった山城である。『臥牛城(がぎゅうじょう)』「豊後竹田城(ぶんごたけたじょう)」とも呼ばれる。岡城の築かれた天神山は標高325メートル、比高95メートル、城域は、東西2500メートル、南北362メートル、総面積は23万4千平方メートルに及んだ。
伝承では、文治元年(1185年)に緒方惟義が源頼朝に追われた源義経を迎えるために築城したことが初めであるという。その山城は、南北朝時代の建武元年(1334年)に後醍醐天皇の支持を受けた大友氏一族[1]の志賀貞朝によって拡張され、岡城と名付けられたとされている。『豊後国志』によると、志賀氏が直入郡に入ったのは応安2年(1369年)以降のことで、岡城に入る前は直入郡にあった木牟礼城を居城としていたという。天正14年(1586年)、 先に耳川の戦いで敗れ衰退した大友氏を下すべく、薩摩の島津氏が豊後府内に迫る快進撃を見せていた中、岡城のみは志賀親次の指揮のもと再三にわたり島津軍を撃退し、親次はその功績から豊臣秀吉より天正15年正月3日付けの褒状を受けている。
先に耳川の戦いで敗れ衰退した大友氏を下すべく、薩摩の島津氏が豊後府内に迫る快進撃を見せていた中、岡城のみは志賀親次の指揮のもと再三にわたり島津軍を撃退し、親次はその功績から豊臣秀吉より天正15年正月3日付けの褒状を受けている。
豊臣秀吉の時代の文禄2年(1593年)文禄の役で大友吉統が秀吉から鳳山撤退を責められ所領を没収されると、大友氏重臣の親次も岡城を去ることとなった。翌、文禄3年(1594年)播磨国三木から中川秀成が移封され、入城後に3年がかりで大規模な修築を施した。…(中略)… 明治維新後、廃城令によって廃城とされ、明治4年(1871年)から翌年にかけて城内の建造物は全て破却され、現在残っているのは高く積み上げられた石垣のみである。昭和11年(1936年)12月16日、「岡城址」として国の史跡に指定され、平成18年(2006年)4月6日、日本100名城(95番)に選定された。平成2年(1990年)には、「岡城公園」として日本さくら名所100選に選定された。」 私たちが訪れたのは夏の終わりで、絶壁の城跡の石垣などもつる草などで覆われ、強者どもの夢のあとを想像させる雰囲気であった。この岡城は上にも書かれているように何度も拡張が行われたようで、極めて広く多くの精密に作られた石垣が残されていた。1枚目の写真は岡城へ上る道に立てられた石碑で春は桜の名所になることをうかがわせる。2枚目の写真は大手門跡である。巨大な石垣はその城の大きさを表している。3枚目はまさに夢の跡を思わせる、草生した石垣である。しかしこの城の城主は7万石であったというから驚く。4枚目の写真は、美しく異例に幅の広い石段で、三の丸への入口であったという。5枚目は二の丸にあり、著名な彫刻家である朝倉文夫作の瀧廉太郎の像である。瀧はこの城跡で何度も何度も遊んだのであろう。そんな滝廉太郎についてWikipediaは次のように伝えている。
私たちが訪れたのは夏の終わりで、絶壁の城跡の石垣などもつる草などで覆われ、強者どもの夢のあとを想像させる雰囲気であった。この岡城は上にも書かれているように何度も拡張が行われたようで、極めて広く多くの精密に作られた石垣が残されていた。1枚目の写真は岡城へ上る道に立てられた石碑で春は桜の名所になることをうかがわせる。2枚目の写真は大手門跡である。巨大な石垣はその城の大きさを表している。3枚目はまさに夢の跡を思わせる、草生した石垣である。しかしこの城の城主は7万石であったというから驚く。4枚目の写真は、美しく異例に幅の広い石段で、三の丸への入口であったという。5枚目は二の丸にあり、著名な彫刻家である朝倉文夫作の瀧廉太郎の像である。瀧はこの城跡で何度も何度も遊んだのであろう。そんな滝廉太郎についてWikipediaは次のように伝えている。
「瀧 廉太郎(たき れんたろう、1879年(明治12年)8月24日 - 1903年(明治36年)6月29日)は、日本の音楽家、作曲家。明治の西洋音楽黎明期における代表的な音楽家の一人である。1879年(明治12年)8月24日、瀧吉弘の長男として東京府芝区南佐久間町2丁目18番地(現:東京都港区西新橋2丁目)に生まれる。 瀧家は江戸時代、日出藩の家老職をつとめた上級武士の家柄である。 父・吉弘は大蔵省から内務省に転じ、大久保利通や伊藤博文らのもとで内務官僚として勤めた後、地方官として神奈川県や富山県富山市、大分県竹田市等を移り住んだため、瀧も生後間もなくから各地を回ることとなった。…(中略)… 明治時代の前半に多くの翻訳唱歌ができたが、日本語訳詞を“無理にはめこんだ”ぎこちない歌が多く、日本人作曲家によるオリジナルの歌を望む声が高まっていた。瀧は最も早く、その要望に応えた作曲家と言えるだろう。彼の代表作である「荒城の月」は、「箱根八里」と並んで文部省編纂の「中学唱歌」に掲載された。また、人気の高い曲のひとつである「花」は1900年(明治33年)8月に作曲された、4曲からなる組曲『四季』の第1曲である。「お正月」、「鳩ぽっぽ」、「雪やこんこ」などは、日本生まれの最も古い童謡作品として知られるが、これらは1900年に編纂された幼稚園唱歌に収められた。また「荒城の月」は、ベルギーで讃美歌になったことも判明した。
瀧家は江戸時代、日出藩の家老職をつとめた上級武士の家柄である。 父・吉弘は大蔵省から内務省に転じ、大久保利通や伊藤博文らのもとで内務官僚として勤めた後、地方官として神奈川県や富山県富山市、大分県竹田市等を移り住んだため、瀧も生後間もなくから各地を回ることとなった。…(中略)… 明治時代の前半に多くの翻訳唱歌ができたが、日本語訳詞を“無理にはめこんだ”ぎこちない歌が多く、日本人作曲家によるオリジナルの歌を望む声が高まっていた。瀧は最も早く、その要望に応えた作曲家と言えるだろう。彼の代表作である「荒城の月」は、「箱根八里」と並んで文部省編纂の「中学唱歌」に掲載された。また、人気の高い曲のひとつである「花」は1900年(明治33年)8月に作曲された、4曲からなる組曲『四季』の第1曲である。「お正月」、「鳩ぽっぽ」、「雪やこんこ」などは、日本生まれの最も古い童謡作品として知られるが、これらは1900年に編纂された幼稚園唱歌に収められた。また「荒城の月」は、ベルギーで讃美歌になったことも判明した。 1901年(明治34年)4月、日本人の音楽家では2人目となるヨーロッパ留学生として、東部ドイツのライプツィヒにあるライプツィヒ音楽院(設立者:メンデルスゾーン)に留学する。文部省外国留学生として入学、ピアノや対位法などを学ぶが、わずか2ヶ月後に肺結核を発病し、1年で帰国を余儀なくされる。その後は父の故郷である大分県で療養していたが、1903年(明治36年)6月29日午後5時に大分市稲荷町339番地(現:府内町)の自宅で死去した。満23歳没。結核に冒されていたことから死後多数の作品が焼却されたという。」
1901年(明治34年)4月、日本人の音楽家では2人目となるヨーロッパ留学生として、東部ドイツのライプツィヒにあるライプツィヒ音楽院(設立者:メンデルスゾーン)に留学する。文部省外国留学生として入学、ピアノや対位法などを学ぶが、わずか2ヶ月後に肺結核を発病し、1年で帰国を余儀なくされる。その後は父の故郷である大分県で療養していたが、1903年(明治36年)6月29日午後5時に大分市稲荷町339番地(現:府内町)の自宅で死去した。満23歳没。結核に冒されていたことから死後多数の作品が焼却されたという。」
彼は少年時代のわずか2年半ほどしかこの地にはいなかったのであるが、岡城跡の印象は「栄枯盛衰」の象徴としてきっと強烈だったのであろう。それを土井晩翠作詞の「荒城の月」に注ぎ込み、あの名曲を作ったに違いない。そんな瀧廉太郎について「瀧廉太郎記念館」を訪れ、そこでは彼の多才さとともに興味深いことを聞いた。この記念館の名誉館長をされていた故・筑紫哲也氏は廉太郎の妹トミのお孫さんだったのである。筑紫氏に親近感を感じてきた私としてはなんともうれしい発見であった。
なお、岡城跡からの帰り道にお土産屋のおじさんに聞いたところによれば、この城跡を“日本のマチュピチュ”として売り出したいと考えているそうである。なんだか分からないでもない気分だ。