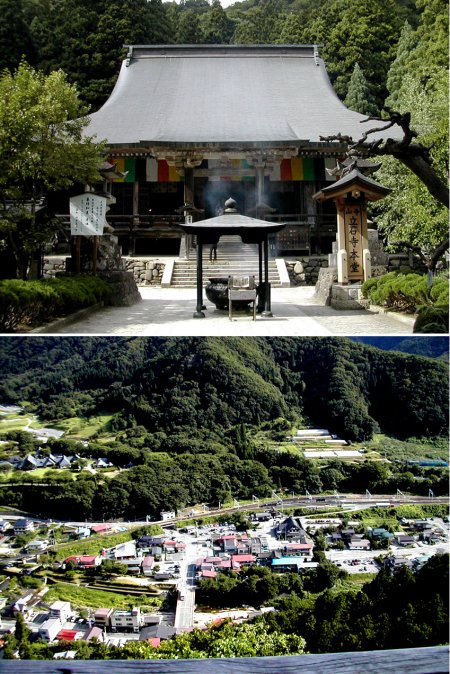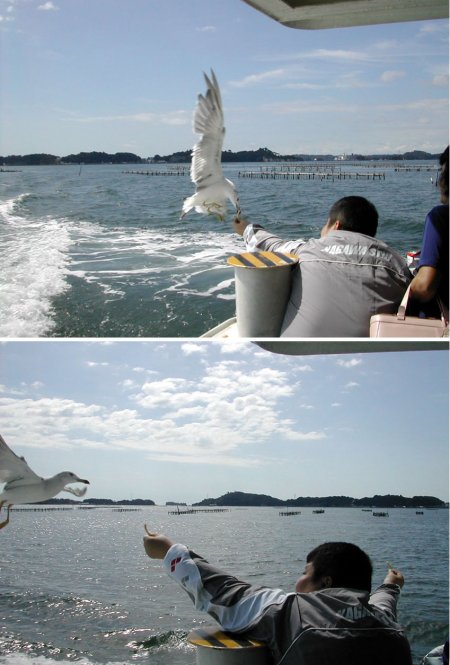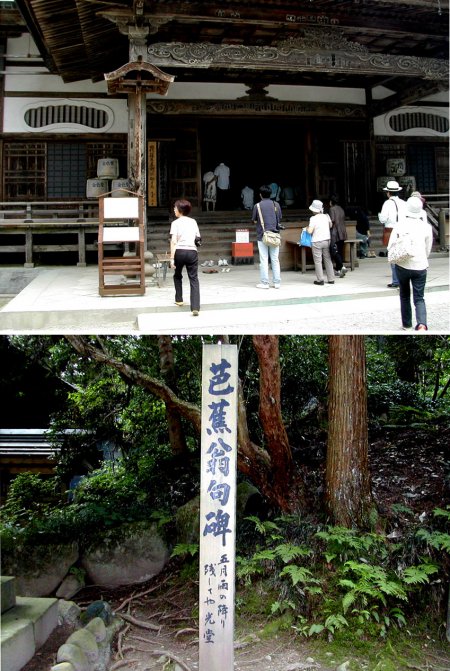[簡易復元] 2011 高槻シティ国際ハーフマラソンに『てっぱん』の人気者が登場!
- 2011/10/29 17:46
 (この記事のオリジナルは2011年1月に書かれたのであるが、ファイルが失われたため、新たに書き直す)
(この記事のオリジナルは2011年1月に書かれたのであるが、ファイルが失われたため、新たに書き直す)
 1996年1月21日、初めてハーフマラソンを走ったのはこの高槻ハーフであった。
1996年1月21日、初めてハーフマラソンを走ったのはこの高槻ハーフであった。 それ以来毎年当たり前のようにエントリーして楽しませてもらってはきたが、2010年11月持病になりつつあった「発作性上室性頻拍」を、大阪大学病院でカテーテル手術に踏み切ったこともあり(http://www.unique-runner.com/catheter1.com )、今回のレースへのエントリーは取りやめることとした。しかし、ジムでのトレーニング仲間が5名参加したので、その応援がてらカメラマンとして参加した。
それ以来毎年当たり前のようにエントリーして楽しませてもらってはきたが、2010年11月持病になりつつあった「発作性上室性頻拍」を、大阪大学病院でカテーテル手術に踏み切ったこともあり(http://www.unique-runner.com/catheter1.com )、今回のレースへのエントリーは取りやめることとした。しかし、ジムでのトレーニング仲間が5名参加したので、その応援がてらカメラマンとして参加した。 一方、2009年秋から始まっていたNHK連続テレビ小説「てっぱん」が終盤を迎え、ヒロイン村上あかりの恋人?「駅伝君」の滝沢薫君がマラソンに挑戦することになった。そのマラソンの撮影舞台が、なんと高槻ハーフだったのには驚いた。そのため長田成哉君と瀧本美織さんが会場の高槻スポーツセンターの陸上競技場に現れ、ゲストランナーがあの高い声で叫ぶ千葉真子さんだったこともあってか、普段以上の大賑わいであった。この2人が千葉ちゃんとともに開会式に登場し、会場はヒートアップ。
一方、2009年秋から始まっていたNHK連続テレビ小説「てっぱん」が終盤を迎え、ヒロイン村上あかりの恋人?「駅伝君」の滝沢薫君がマラソンに挑戦することになった。そのマラソンの撮影舞台が、なんと高槻ハーフだったのには驚いた。そのため長田成哉君と瀧本美織さんが会場の高槻スポーツセンターの陸上競技場に現れ、ゲストランナーがあの高い声で叫ぶ千葉真子さんだったこともあってか、普段以上の大賑わいであった。この2人が千葉ちゃんとともに開会式に登場し、会場はヒートアップ。 それを見届けて、私は撮影場所に選んだ10キロ地点に自転車で向かった。その場での撮影を終わって再び、スタート地点に戻り、ゴール前での仲間たちの苦しい表情を追った。写真を紹介しよう。1枚目の写真は壇上に上がった長田君ともちろん千葉ちゃんで、2枚目はゲスト席に座っている千葉ちゃん、長田君そして瀧本さんである。3枚目から5枚目は仲間たちの10キロ地点とゴール地点での写真で、タイムはそれぞれであるが全員無事完走してばんざ~い、めでたしめでたしで終了した。
それを見届けて、私は撮影場所に選んだ10キロ地点に自転車で向かった。その場での撮影を終わって再び、スタート地点に戻り、ゴール前での仲間たちの苦しい表情を追った。写真を紹介しよう。1枚目の写真は壇上に上がった長田君ともちろん千葉ちゃんで、2枚目はゲスト席に座っている千葉ちゃん、長田君そして瀧本さんである。3枚目から5枚目は仲間たちの10キロ地点とゴール地点での写真で、タイムはそれぞれであるが全員無事完走してばんざ~い、めでたしめでたしで終了した。